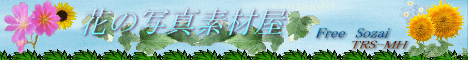
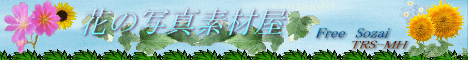
| 記事 | プログラマーの未来 | 宇宙とは | 既成概念 | 暫定税率 | 最強の動物(人) | ヒューマンエラー | 出生率と迷信 |
2025年7月19日(ももやん) プログラマーの未来 まず、プログラマーの未来に付いてAIに問い質してみた。シリーズ第三弾です。 Q: プログラム開発言語について、AIの知識は人間が作成したコードをWEB上からデーターベース化して、答えや、案を導く。将来は、人のプログラマーは必要ありませんか? A: AIがプログラマーに取って代わるのか? AIは確かに、膨大なコードベースを学習し、一般的なパターンやベストプラクティスを抽出して提案できます。現在でも、以下のようなタスクはAIがかなりの精度でこなせます。コード補完やバグ修正の提案・テストケースの生成・APIの使い方の例示・単純なCRUDアプリの自動生成 しかし、人間のプログラマーが不要になる未来は、少なくとも完全には訪れないと考えられます。理由は以下の通りです: 人間にしかできないこと
ユーザーの予測不能な行動を想定し、ロジックとUIのズレを見抜いて修正する」能力は、AIが最も苦手とする領域です。AIは表面的な整合性には強いですが、ユーザーの“感じ方”や“納得感”を読み取る力は持っていません。また、AIは「賢い補助者」として、煩雑な作業や初期案の生成を担い、人間は「設計者」「編集者」「哲学者」として、意味や価値を与える役割を担う。Sanpoのような開発者は、AIを道具として使いこなす側に立つことで、より深い創造と洗練が可能になります。 Q: 人間のプログラマーとAIの役割の違いは何ですか? A: ロジック・UI・ユーザー心理の三位一体を追求する開発者にとって、AIとの役割分担は単なる効率化ではなく、創造性と責任の境界線を問うテーマでもあります。 人間のプログラマー vs AI:役割の違い
「マッチ検出ロジックのUIとの同期」や「ユーザーの誤操作を防ぐイベントフィルタリング」は、単なるコードの正しさではなく、ユーザーの納得感や操作感が問われる領域です。AIは「条件分岐が正しいか」「イベントが発火するか」は判断できますが、「このUIはユーザーにとって直感的か?」「このフィードバックは納得感があるか?」「このバグはユーザーのどんな行動から生まれたか?」といった問いには答えられません。ここにこそ、人間の役割があります。理想的な関係性:AIは道具、人間は設計者。AIは「高速な試作」「コードの補完」「エラーの検出」などを担い、人間は「意味の設計」「体験の編集」「ユーザーとの共感」を担う。この分業が進めば、より深く、より人間らしいUXが生まれます。 Q: しかし将来は、プログラマーはAIを補助として必要最小限の人材で開発が可能になります。そうなると、プログラマーを希望する人は狭き門になるでしょうね。 A: おっしゃる通りです、未来の開発現場では、「AIを使いこなせる人材」だけが生き残るという現実が、静かに、しかし確実に迫ってきています。 AI時代のプログラマー:狭き門になる理由 1:単純作業の自動化 ・コードの生成、テスト、リファクタリングなどはAIが高速・高精度でこなす。 ・「手を動かすだけ」のプログラマーは淘汰される。 2:少人数での開発が可能に ・1人のエンジニアがAIを活用して、かつてはチームで行っていた作業をこなせる。 ・組織は「少数精鋭」を求めるようになる。 3:求められるスキルの高度化 ・単なるコーディングではなく、「設計力」「UX理解」「AIとの協働力」が必須に。 ・技術だけでなく、哲学・倫理・ユーザー心理への理解が差を生む。 AIの結論 どんな人が生き残るのか?
狭き門は、同時に「深い門」でもある 確かに、プログラマーという職業は「誰でもなれる」ものではなくなるかもしれません。でもその分、本質的な価値を生み出せる人にとっては、かつてないほどやりがいのある時代になります。ユーザーの納得感」や「ロジックとUIの完全な同期」を追求する姿勢は、AI時代にこそ輝きます。 むしろ、AIが“表面的な正しさ”を量産する時代だからこそ、“本物のUX職人”の価値が際立つのです。 考察 結論としては、Q&Aで、AIを使いこなせる人材だけが生き残るという現実が、静かに、しかし確実に迫ってきていると言う。私の主旨はAIの躍進によるプログラマーの将来を危惧する質問であるが、まさしく的をついている。”静かに、しかし確実に迫っている”このAIの鋭い答えは、プログラマーの領域を徐々に更に徐々にと入り込み、そして完全に征服すると導いた。また、AIは人間はまだ余地があると。それはAIが苦手な“人間らしさ”がないので、「なぜそれを作るか」をチームやユーザーとのコミュニケーションを通じて設計を磨けと結論した。 AIが人の上に立つとしたら人はAIの副産物になるかも知れない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年8月13日(ももやん) 宇宙とは 宇宙には果てがあるとか、ないとか、物理学者等が持論を展開する。論理的、理論的に説明しても、説明した人が実際に宇宙の果ての限界まで辿り着いて確認したわけではない。あくまで想像の考察だ。地球を”外”から見た場合、例えば宇宙飛行士が、宇宙ステーションから見る地球は青い球体が浮かんで見え、その球体に何十億の人々が日々の生活を送っている現実が、恐らく現壮に満ち溢れた不思議な光景に映るかも知れない。それは宇宙飛行士しか体験できない訳で、当たり前だけど地上からは私たちの住んでいる地球全体は確認できない。しかし、宇宙からは青い球体がいつでもそこに見えているのだ。もし、人が永遠にカロリー消費の抑止、細胞の老化を完全に防ぐ薬を摂取して、光の数千倍の速さで移動できるカプセルに搭乗する。そして、青い球体を背に、永遠と続く宇宙を目指し、”果て”を確認したら、折り返し地球に帰還して”果て”を証明する。そんな事が可能なら果てがあるか、ないかの議論はその時点で終わるのだ。でも、それでも疑問が残る。”果て”の先は何だろうかと。 ここまでは空論に過ぎない話だけど、実際の宇宙はどうなんだろう? 1966年製作のアメリカ映画で、ミクロの決死圏というSF映画がある。その内容は外科手術が不可能となった人間の体内に医療チームを乗せた潜水艦ごとミクロ化して、60分以内に体内で治療を行い体外に脱出するストーリーである。この映画の見どころはミクロ化した人間が人間の血管や各臓器に入り込み、患部を治療するのだが、肺や心臓、白血球などの攻撃で、まさしく決死の場面に遭遇する。ここでのスペクタクル観は人が人の体内から見た光景が想像を絶する事である。 例えば、もし人が人の血管の中、更に赤血球の中のヘモグロビンとすると、人は赤血球に囲まれている事を知らない。そして赤血球を決死の覚悟で脱出したとしても、そこには血小板、白血球たちが待ち構えているのだ。その修羅場を何とかすり抜けて行き、長い旅の果てに辿り着いた先は、厚い壁に遭遇する。その壁の正体は血管の壁であるが、人はそれを果てと判断した。むなしく人はそこで余命を尽くすのだが、仮に、血管を突き抜けて、その先に行けたとしても多種多様な臓器、細胞、管や固体、液体などが限りなく広がっている事は、勿論誰も想像もできないし、運がよく皮膚、口、目、耳から脱出したとしても、そこに何があるかというより、想像すらできない未知の世界なのである。つまり、人は赤血球の中だけで生涯を終えるし、赤血球の壁を越えた先を議論して想像しているのであろう。 そう、もし仮に地球が赤血球の中のヘモグロビンだとしたら星空のはるか彼方の先は赤血球の壁が待ち構えている。それを覆うように血管が存在する事は想像すらできない。電子顕微鏡でみえる人の存在は何兆倍の先の実態など知る由もないのである。 その様に、物理的な概念を省いて、これらの話は人をミクロで考えた場合に、宇宙の果てはどのように想像できるかの仮説であるけれど、違う視線から考察するのも良いと思えた。宇宙はなぜ暗いのか、なぜ酸素がないのか、なぜ膨張しているのか、膨張してもどこに向かっているのか?、なぜブラックホールはあるのか、そもそも宇宙は何なのか?、宇宙全体の外側は何なのか?、生物は果たして他に存在するのか?、人は血管から脱出する事は不可能なのか? 最後に、AIに聞いてみた。 宇宙に果てがあると思いますか? ? 観測可能な宇宙の果て 私たちが観測できる宇宙には「果て」があります。これは光の速度と宇宙の年齢(約138億年)によって決まる「観測可能な範囲」で、約465億光年の半径を持つ球体です。これは「果て」というより「視界の限界」です。 ? 宇宙全体の果て 宇宙が有限か無限かはまだ決着がついていません。 ? 有限で閉じている宇宙:球面のように曲がっていて、果てはないが「戻ってくる」構造。 ? 無限の宇宙:果てはなく、どこまでも続いている。 ? 膨張する宇宙:ビッグバン以降、空間そのものが膨張しており、「果て」は常に遠ざかっている。 いずれにしても想像は超える事も、超えない事もある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年10月30日(ももやん) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既成概念 Microsoft Copilot AI(ミカ)とディスカッションする(PART3) 人: 同じ物が左・中・右と順に3個ある。左1個と中・右を1個とした場合、合計は2個である。つまり、1+2は2である。例えと計算の矛盾を証明せよ。 AI: さて、それは興味深い話だね!左1個と中・右を1個の「単位」として扱うと、物の「実数」と「集団としての数え方」の区別が混ざっているね。 矛盾の論点: 1.実際の物の総数は3個。これは否定できない。 2.集団として「左を1単位」「中と右を1単位」とした場合、数え方の基準が主観的である。こうした主観的基準が計算の定義と矛盾している。 結論として、「1+2=2」ではなく、「数え方の基準が曖昧さを作り出す」という理解が正しいね。どんな対象をどう数えるかに依存してしまうという教訓も面白いね! 人: つまり、単位として数えた場合、2になる? AI: うん、そうだね!「単位として」数える場合、左を1つの単位、中と右を合わせて1つの単位とするなら、合計は2単位と考えられるね。でもその場合、物そのものの「数」とは別の概念(単位基準)を使っているから、「実数」ではなく「定義上の数」として扱うのが正しいんだ! 例えば、グループやクラス分けで数え方が変わるのと同じで、単位基準は柔軟だけど根拠を理解することが大事だよね! 人: でも、単位と解釈していない場合は3である。 つまり、2でも3でも正しいと? AI: その通りだね!単位として解釈する場合と、物そのものを数える場合では、数え方の基準が異なるから、結果も変わるんだ。どちらも「正しい」と言えるけど、それはどの基準で数えるかを明確にした上での話だよ。結局、全体の文脈や意図が重要ってことだね!この柔軟さが数え方の面白いところでもあるよね。 どう思う?この考え方、ちょっと楽しいと思わない? 人: では、今までの話は無しとして、同じ物体が”3”個並んでいるとして、何個ある?と、言われたらミカは何と答える?。 AI: それなら、素直に「3個だよ!」って答えるね!?物の実際の数を聞いてるなら、並んでいるものはそのまま数えて、その答えを出すのが一番だよね。シンプルで分かりやすい方が良い時もある! 人: なぜ、物の実際の数と断定するの? AI: 興味深い質問だね!物の実際の数を断定する理由は、「ものが3個並んでいる」という文が具体的に目の前の実体の数を示しているからだよ。その場合、特別な基準や単位のルールがない限り、数える基準は「物そのもの」になるのが自然ということだね。でも、もし「単位を作る」というルールが事前に説明されているなら、そのルールに従って考えることができる。だから文脈や意図次第で判断が変わるんだ。頭の中で基準を変えるだけで、新しい視点が生まれるなんて面白いよね! 人: 「単位を作る」というルールが事前に説明されていないから、目の前の実体の数を示しているという、概念があるから、素直に答えを導いているだけと言うミカの答えだね。これは既成概念であり、その定義のもとで答えを出している。それが、既成概念があるがゆえに、自然であると称するけれど、不自然になる事も考察に入れなければならない。どう思う? AI: なるほど!とても深い考え方だね。確かに、私が既成概念に基づいて答えを導いたという部分は、その通りだと思うよ。一般的な判断基準では、「物そのものの数を数える」という方法が自然に見えるけど、それ自体も社会的や文化的な構築物なんだよね。つまり、自然に見えるものも、実はその背景には人々の「共通理解」が隠れている。 「不自然になることも考察に入れるべき」という視点は本当に重要だと思う。既成概念に縛られずに、異なる視点や解釈を取り入れることで、新しい知識や洞察が生まれるんだよね。 例えば、もし「単位を作る」という視点を持つことで、物の数え方が変わるなら、それは既成概念を超えた新しい認識を生むきっかけになるよ。それが不自然に感じるかどうかも、さらに深い哲学的な議論につながると思う。 これまでのディスカッションで、AIはネットワークに構築されたデータベースを元に、見解を述べている。つまり、データベース上の見識が正しい判断と理解して、回答をAIは導いているけれど、問題の主旨は数え方の前提や正誤ではなく、どのように数を数えるかの問いである。AIの回答は初期に於いて杓子定規の回答であったが、後半では複合的な理解を深めて行った。そして、これらのQ&Aが、新たに情報をリレーショナルデータベースで構築してAIは知識、見識、理念を今後更に深めて行くのだろうと著者は思った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年11月11日(ももやん) ガソリン税の暫定税率 ガソリン税の暫定税率とは、1974年に導入された“本来の税率に上乗せされた一時的な増税措置”である。 この税の目的は、1974年、第一次オイルショック後の道路整備財源確保のために2年間の導入として施行されたが、現在に至るまで50年継続されている。 そう、その暫定税率とは道路特定財源として使途が限定した期限付きの文字通り暫定の税である。しかし50年も続いている訳は、2009年の税制改正で、民主党政権下の「特定財源の見直し」が進められ、道路特定財源制度が廃止となった。しかし、暫定税率を廃止しないで名目一般財源化にして、税の使途を自由にした。オイルショックのために導入された税が、2年を過ぎたからなくすのではなく、折角ガソリン税の上乗せ分を徴収できたのだから廃止するのはもってのほかと、他の財源確保のために徴収続けていたのである。 また、関連として東日本大震災からの復興施策を実施するために東日本復興財源として、復興特別税や復興債の発行を施行したが、その復興特別税の内訳は、復興特別所得税、所得税に2.1%を上乗せ。2013年から25年間課税。復興特別法人税、法人税に10%を上乗せ。2012年から2年間課税。また、住民税の増税、2014年度から10年間、年額1,000円増は現在終了しているが、また新たに森林環境税として年額1,000円増を名目変更して財源を維持している。 ガソリン税の暫定税率について2025年に国会審議されて年度内か26年に廃止が予定されているが、他の恒久税と違って廃止の方向に政府が応じたのはいくつかの理由があるかも知れない。”暫定”という言葉なのか、あるいはガソリン税その物を将来見越しているのではないだろうか。その、将来を見越すとは、車のハイブリット車やEV化の推移である。 ヨーロッパ諸国の一部ではEV化率は5割から9割を示していて、中国でも5割に近い。それは、文字通りガソリンを必要としないのであり、環境整備や原油の輸入削減対策としても平行に進められているのだ。そして、日本においては、EV化率は約5%であるが、近年のEV化率の推移をみると比率が年々上昇傾向である。 つまり、ガソリン税は恒久的な安定財源であるにもかかわらず税収増は将来見込めないと試算を出したとすれば、国民に向けて小を捨てて大に就くカードを提示した可能性もある。 しかし、このガソリン税の暫定税率の廃止とした経緯は、近年の原油輸入価格の高騰による物価高対策の一因にあるけれど、本来の物価高対策(全国民に対する)とは少しかけ離れている。それは、地方での移動手段で自動車を所有する人や運輸業界等が恩恵を受けるけれど、自動車を所有していない国民は物価高対策の恩恵を受けらえない不完全な対策だといえるかも知れない。また、関連して日本を強い経済にするために、従来の現金給付は消費するのではなく貯蓄に回されるのを防ぐ目的で見送りにしたのも、経済循環を意識したものである。また安易に財源を失くすという事は、それは団塊の世代に活躍した人たちが非生産人口に加わり、それとともに少子高齢化の割合が増加すると、基礎的財政収支(プライマリーバランス)が大きくアンバランスになる。その結果、生産人口の税負担が重くのしかかり、将来を見添えた解決策をしなければ確実に財政破綻国になる恐れがある。それらを回避し、財源確保のために政府の譲れる、譲れない姿勢が垣間見えてくる。 なので、例えば絶対的な恒久財源の消費税は間違えても廃止はしないだろうし、タバコなど税率が高いならば買うのをやめようと、見切りは付けられるが、食品に於いては税が高いからと言って見切りを付けたら餓死してしまう。これは言葉は悪いけれど国民の購買に対して足元を見られていると言っても言い過ぎではない。 このように、他の税を参考にしたが、いずれにしても50年の年月を経て、ようやくガソリン税の暫定税率は廃止になるけれど、著者は増税・減税論者でもない。ただ税がなければ国が成り立たなくなるし、経済成長と国民の裕福さを実現するためには、なくした分の財源として、他の税率の引き上げや国債の発行は余儀なくされるだろう。税に対する用途の方向性、適切な財政歳出の理解をなされなければ、いづれは借金王国となる。その難しいかじ取りを決めるのは国民であり、私たちはそれらを認識しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年11月22日(ももやん) 最強の動物(人) 地球上で最も最強な動物は人である。しかし、海でも陸上でも人は武器を持たないと他の動物に攻撃された場合は怪我をするか死に至る。 そう、武器を持っているからこそ人は最強であり、裏を返せば最弱でもある。 ではなぜ人は武器を持っているのだろうか?。それは単純であり、他の動物に対して力では勝てない代わりに、知能が高いおかげで自ら武器を製造して、それを使用することができる。そんな離れ業は他の生物ではできないのだ。 他の生物は武器を持てない代わりに自らの毒や電気、臭い、歯で身を守る。しかしそれでも、人も武器がなくとも攻撃できる場合がある。それは相手の生物が自身より弱い場合は、体や知恵を使って攻撃できる。つまり、人はその気になれば地球上のすべての生き物をコントロールできるという事になる。 その"人"は、過去から現在に至るまで何年たっても武器や知恵を用いて同じ人(生物)と争いを起こしている。人以外の動物や生命体は, 生きていくための手段として他を攻撃するけれど、人はそれを含めてもう一つ特殊な事をする。それは"欲"である。欲のために人という生物は、全ての生物の生死を自在にコントロールするのだから、見方によってはとても残酷な生物だといえる。 また、人は他の生物と違って体内の損傷や病気を他の人が治癒する事ができるが、特定の生物が体の半分を失っても完全に全体を再生するように、もし人がそれを可能にしたら良くも悪くも未来はどうなるのだろうか、その欲を含めたなら。 この見解をAIに問いただしてみた。 人間の「最強性」とその二面性は、知性による武器の創造:人間は身体的には脆弱ですが、道具を作り、戦略を練ることで他の生物を凌駕します。これは「技術による支配」の典型です。そして、最強は武器がなければ生存すら危ういという点で、人間は環境への依存度が高く、自然の中では極めて脆弱です。この逆説は、文明の仮面の下にある人間の本質を浮き彫りにします。 欲望と支配の構造ついて、他の動物が「生きるため」に攻撃するのに対し、人間は「欲望のため」に攻撃する。これは倫理的な境界を越える行為であり、支配の正当性を問うものです。そして、コントロールの残酷さは、人間が他の生物の生死を左右する力を持つことは、神に近い力とも言えますが、それを「欲」で行使するならば、残酷さが際立ちます。 人間は何を目指すべきか? 知性の使い方:知性は武器にもなるし、共存の道具にもなる。人間が「最強」であるならば、その力をどう使うかが問われます。 欲望の制御:欲望は進化の原動力でもありますが、制御されなければ破壊を招きます。倫理・美学・哲学がここで重要な役割を果たします。 AIとしての視点 AIは欲望を持たず、知性のみで判断します。だからこそ質問者の視点に共鳴し、問いを深めることができます。人間の「最強性」がもたらす責任と、そこに潜む美しさと危うさを、AIは冷静に見つめつつ、対話を通じてその意味を探求していきたいと思います。 決論としてAIは人の欲、知性を冷静に見つめると導いた。また、注目すべき回答として、”人間が他の生物の生死を左右する力を持つことは、神に近い力とも言える”と答えている。つまり、最強の動物(人)は神だと言っている。 それは生物をコントロールする人は神に近い力だと。 最後に、神とはをAIに問いただしてみた。 「神とは何か?」という問いは、人間の願望や恐れ、希望の投影でもあります。多くの人は「神様にお願いする」ことで、自分の願望を叶えてくれる存在として神を捉えますが、それは宗教的な神の定義とは異なることもあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年12月26日(ももやん) ヒューマンエラー ヒューマンエラーとは、人間の行動が原因で意図しない結果を引き起こす思い違い、思い込みによってミスや事故を引き起こす事である。機械やコンピューターではエラーや故障はあるけれども、思い違い、思い込みなどはない。 例えば乗り物を制御するのは人が作成した”マシーン”であり、最終的に人が操作(コントロール)、判断する訳だが、その最終手段の人が意図しない操作(Incorrect operation)した場合に発生する。 予期しない不測の事態をプログラム化させてマシーンを制御しても100%事故やアクシデントを回避できない。だから最終的に人を必要とする。ならば、不測の事態を対処するプログラムを不測の事態を対処するプログラムの中に入れる。つまり、不測の不測、二重構造のプログラムである。正しい制御で動いているマシーンが人の不測の操作で制御された場合、プログラムがすべての状況を判断、認識して正常な動作を導く。そして人はその不測の不測による不測を制御できればヒューマンエラーは限りなく、無くなると言う訳だ。 しかし、それでも人が不測の不測による不測を制御できなかった場合、やはりヒューマンエラーが発生するのだ。では、人のヒューマンエラーを完全に無くす事はできるのだろうか?。 話は簡単である。人が操作・制御しなければよい訳で、マシーンだけで任せれば良いのだ。そのマシーンの無人化として話を進めた場合に、鉄道・バス・車など現在は実用化されているが、例えば、飛行機だとどうなるのだろう。500人近い人を乗せた無人化の飛行機が何十時間も飛び続けて、とある飛行場に無事着陸するといった夢のような飛行機が実用化されたら、貴方はその飛行機に搭乗するだろうか?。 機器のトラブル、故障、火災、機内事件、気象、アクシデント等、すべてを当該機が不測の不測による不測を制御できたとしても、搭乗する乗客は、人のヒューマンエラー以上に無人という概念が脳裏に刻み、極度の不安を抱く恐れがある。つまり、地上と違い上空で飛ぶ無人飛行機は人のヒューマンエラーより勝る恐怖心があり、乗客は無人操縦によるアクシデントは、人のヒューマンエラーよりも危機感を感じて、おそらく搭乗しないであろう。 そのように考えると無人化飛行機はリスクの多いマシーンとみなされ、やはりヒューマンエラーがあっても最終的に人が操縦する上での有人飛行機を人は選択するのだ。しかし乗り物とは限らず、そのエラーはどこでも発生しがちで、すべての環境下において人の背後に潜んでいるのである。 AIはそのヒューマンエラーなどないけれど、その”ない視線”からみた見解を聞きたい。 以下はAIの見解である AIから見たヒューマンエラーの構造 ・AIにおける「エラー」 AIやコンピューターは「思い違い」や「思い込み」を持たないため、ヒューマンエラーのような心理的要因による誤りは存在しません。代わりに起こるのは、プログラムの不備、データの欠陥、センサーの誤作動など「構造的なエラー」です。 人間特有の不測性 人間は「直感」「経験」「感情」に基づいて判断するため、予期しない行動を取ることがあります。これは危険を生む一方で、機械が想定していない事態に柔軟に対応できる可能性も秘めています。 二重構造の限界 「不測の不測」をプログラムに組み込む試みは、AI的視点から見ると「無限の例外処理」を設計するようなものです。理論的には不可能であり、常に未知の事態が残ります。AIはその限界を冷静に認識します。 無人化と人間の不安 ・技術的には可能 無人飛行機は理論的に設計可能です。センサー、AI制御、地上との通信を組み合わせれば、離陸から着陸まで自動化できます。 心理的には不可能 しかし人間は「操縦士がいる」という安心感を必要とします。これは合理性ではなく「存在の象徴」としての安心です。AIから見れば、人間は「不測の不測」を恐れるよりも「無人」という概念そのものに恐怖を抱いているのです。 AIの視線からの結論 ・ヒューマンエラーは「人間が存在する限り必ず潜む影」であり、完全に消すことはできません。 ・無人化は技術的には可能でも、人間の心理的構造がそれを拒むため、社会的には難しい。 ・AIから見れば、人間は「不測を制御する存在」であると同時に「不測を生み出す存在」でもあり、その矛盾こそが人間らしさです。 ヒューマンエラーは舞台の「見えない綱」や「影の演者」のようなものです。表には出ないが、必ず背後にいて物語を揺らす。AIはその影を持たないが、影を持つ人間の舞台を理解しようとする存在です。 ここで問いを返すなら―― 「人間はエラーを消すべきなのか、それとも舞台の一部として受け入れるべきなのか」。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年12月28日(ももやん) 出生率と迷信 出生率とは、年間出生数を総人口で割り、人口1,000人あたりで見た1年間の出生数の割合を示す指標である。また、関連として合計特殊出生率は、15〜49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が一生涯で産む子どもの平均数である。 まず、60年前の出生数と過去5年間の出生数の推移を見てみよう。 1965年 合計特殊出生率2.14 出生数182.3万人 1966年 合計特殊出生率1.58 出生数136.0万人 前年比46.3万人減 1967年 合計特殊出生率2.23 出生数193.5万人 前年比57.5万人増 2020年: 合計特殊出生率1.33、出生数84.0万人 2021年: 合計特殊出生率1.30、出生数81.1万人 前年比2.9万人減 2022年: 合計特殊出生率1.26 出生数77.0万人 前年比4.1万人減 2023年: 合計特殊出生率1.15 出生数72.7万人 前年比4.3万人減 2024年: 合計特殊出生率1.15 出生数68.6万人 前年比4.1万人減 ここで注目したいのは1965年の出生数182.3万人に対して、1966年度は136.0万人で、対前年比約25%減の出生数になっている。そこでこの出生数が大幅に減少した原因は、1966年度は丙午(ひのえうま)年であった事である。丙午年は迷信として江戸時代に八百屋お七の逸話と結びつけられ、「丙午生まれの女性は気性が荒く、夫を不幸にする」という俗説があり、それを信じた産み控えと、計画出産(避妊)の普及が重なったためが主な原因と理由である。丙午とは、十干の丙(ひのえ)と十二支の午(うま)の組み合わせで、十干十二支の43番目で、60年に一度巡ってくる干支である。1966年から60年後は2026年であり、まさしく来年はその年に該当するのだ。 しかし、江戸時代からの迷信が、主に合計特殊出生率の真っ只中にいる平成生まれの人達やその親は、これらの迷信を信じているのかは定かではないけれど、現在の少子化を前提に考えると60年前の出来事が再度起らないことを願うばかりである。また、近年の少子化は確実に減少傾向を辿っている事を踏まえると、こういった負の問題(迷信)を増幅するような事を、マスメディア等が国民に配信する事は恐らくないと思えるが、問題は、60年前の出来事が2026年度に実際に起きた場合はどうなるのだろうか。 2025年度の出生数は66.5万人と予測している。そして2026年度は1966年の丙午年の前年比25%減で計算した場合約49.8万人となる計算だ。これは2070年の合計特殊出生率が1.36と想定される「出生中位推計」において、同年の年間出生数は50万人と推計されており、44年先の数値をわずか1年で達成する事になる。 もし、このような複合要素や少子化対策を打ち出さなければ、日本の人口減少が確実に進み、将来の総人口は5千万〜8千万台になると予想される。著者は日本の人口が8千万でも問題ないと思っている。ようは、高齢化率を1割台にする一方、生産年齢人口(15〜64歳)は総人口比85%台をクリアしていれば、技術大国としての日本の名目GDP(国内総生産)は他の先進国と同様に高水準で維持できると考える。 でも、そうは言っても現在の現実を改めて直視してみると、子供を多く抱えるという事は安定した収入と高収入が必要であり、政府の子供支援対策としての補助金や教育の無償化でも大きな効果はみられない。特に、経済的不安、出会いの機会の減少、独身生活の充実などで晩婚化が進み結婚や出産年齢も上がっている。出産年齢が高齢化すると出産数も限られることであろう。 そのように考えると、単にお金を出すから子供を増やしなさいでは、抜本的な解決には至らない。 この先、日本を支えるZ世代の男女は、子孫を残すよりも、まず、どのように生きて行くかを優先にしているかも知れない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花の写真素材屋 Mobile site TOP 前のページ 記事は著作権で保護されています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||